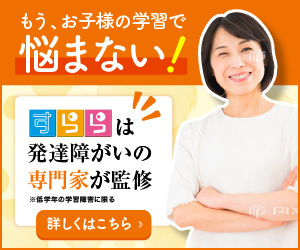ADHDやASDなどの特性をもつお子さんの中には、とても優れた知的能力を持つ子も多くいます。
しかし、学校という集団の環境や人との関わりがうまくかみ合わず、その力を十分に発揮できなかったり、学習への意欲が下がってしまうことも少なくありません。
親御さんの中には、「できれば特別扱いではなく、ほかの子と同じように学校生活を送らせたい」という思いから、「学校に行くことが絶対!」とつい無理をさせてしまうケースもあるでしょう。
こうした中で親御さんもお子さんも大きな負担を抱えているご家庭も少なくありません。
しかし、最近では自宅学習でも出席扱いになる制度が広がっています。特に注目されているのが、個々のペースに合わせて基礎学力をしっかり身につけられる無学年式のオンライン教材「すらら」です。
この記事では、「すらら」が発達障害のあるお子さんに合う理由をはじめ、出席扱いの活用事例や実際の体験談、他教材との違い、家庭でできる工夫までを詳しくご紹介します。
学校に行けない日は思い切ってお休みしても、「勉強の遅れ」や「出席日数」の心配をすることなく、子どものペースで学校生活をサポートしたい。そんな親御さんに、ぜひ読んでいただきたい内容です。
ゆっくりペースのお子さんにおすすめ!
すららとは?発達障害の子どもに向けたオンライン教材の全体像
すららとは?(対象年齢・教科)

すららは、小学1年生から高校生まで幅広い学年に対応したオンライン教材です。
国語・算数(数学)・英語・理科・社会など主要教科をカバーし、インターネットにつながるパソコンやタブレットがあれば、どこでも学習できます。
- 理科・社会の対象範囲は小学3年生〜中学3年生
- 英語の対象範囲は中学1年生〜高校3年生まで
さらに、すららは「AIを活用」したアダプティブラーニング教材です。学習履歴や正答率をもとに、AIが苦手分野を自動で分析し、必要に応じて基礎から学び直しできるカリキュラムを提示。得意分野は先取り、苦手分野は戻って復習するなど、一人ひとりに合った進め方が可能です。
一人ひとりの特性に合わせて学習できる「無学年方式」

すららが取り入れている「無学年方式」は学年を超えて勉強できる学習方法です。
今の学年にとらわれず、苦手分野は基礎までさかのぼって学び直し、得意分野はどんどん先取り学習ができるため、分野によって理解度の落差が激しいお子様にとって非常に取り組みやすくなっています。
発達障害専門機関「子どもの発達科学研究所」との共同開発

すららの教材は、発達障害支援に関わる専門機関「子どもの発達科学研究所」と共同開発されています。読み書きが苦手なお子さんにも配慮し、文字の大きさや色、画面レイアウト、説明の仕方など細部まで設計。専門機関の知見を取り入れることで、特性に合わせた学びやすい教材になっています。
キャラクターが登場し、ゲーム感覚で学べる「多感覚」学習教材

授業はキャラクターがアニメーションで教えてくれる形式で、ゲーム感覚で進められます。
学校の授業と違うことから「今日は学校に行けなかった」という日も気持ちを切り替えて取り組めるところも評価されています。(学校に行けなかった日に学校と同じような教材を取り組むのは気が進まないですよね)
発達障害の子どもは視覚や聴覚からの情報が理解しやすい場合が多いため、色分けや音声ガイド、図解を取り入れた画面構成は大きなメリットです。

保護者も安心!「伴走型」サポート体制
保護者の強い味方「すららコーチ」
学習の進捗や課題を見守る「すららコーチ」は、親御さんにとっても心強い存在です。
一般的な教材では学習の進捗報告や簡単なフォローが中心ですが、すららではお子さんのやる気が下がったときの声かけや、家庭学習の進め方の相談にも応じてくれます。
特にすららは「不登校」や「発達障害」のお子さんに採用される実績も多いため、アドバイスにも知識と経験が活かされています。そのため、ひとつひとつの言葉に説得力があり、保護者にとっても大きな安心材料になります。
進捗状況だけでなく、お子さんの特性や学習スタイルまで踏まえたうえで、「どの単元を優先するべきか」「褒めるタイミング」など具体的なアドバイスをもらえるのも魅力です。
すららコーチ「多賀谷先生」のご紹介

多賀谷先生は、自身のお子さまも学習障害があり、一般の塾では馴染めない子どもたちのことを理解し、特性を活かした指導で保護者からの信頼も厚い先生です。
発達障害の家庭学習で大切なこと
発達障害は、知的障害ではありません。
勉強すれば高校へも行くことが可能です。学習の遅れ方もさまざまなので、まずは遅れの度合いをしっかり確認し、特性を詳しく教えてもらいます。
学校や家での様子などを保護者から聞き取りして、その子に合った学習の進め方を考えていきます。一人ひとりに的確にアドバイスするためにすららの学習履歴画面を見ながら具体的な改善策を保護者にお伝えして、保護者にも関わってもらうようにしています。
家庭学習はもちろんスムーズにはいきませんが、保護者が根気よく向き合っていけば、必ず子どもは変わっていきます。我が子の将来の可能性を開花させてあげたいというのが親心です。
すららで学び、普通教室に入ることができたら、お子さまが将来自分のやりたいことを見つけていくのに役立つと思います。すららコーチは保護者を支えるアドバイザーとなりますので、ご遠慮なくご相談ください。
引用元:すららコーチ「多賀谷先生」
すららの実績

すららは、多くの教育現場で信頼される教材です。
- 約2,500校の塾・学校が導入
- 特別支援学校・特別支援教室に多数の導入
- 経済産業省が進める「未来の教室実証事業」に採用
2012年の文部科学大臣賞をはじめ、社会課題解決賞や世界発信優秀賞など、教育や社会的取り組みで高く評価されてきました。2019年には経済産業省の「未来の教室実証事業」にも採択され、その品質は公的にも認められています。
現在では全国約2,500校の塾や学校で導入され、特別支援学校や特別支援教室でも多く活用されています。発達障害や不登校など、学びに課題を抱えるお子さんも安心して取り組める環境づくりが評価されているのです。
「家でも勉強できる環境を整えてあげたい」「学校に行けない日でも学びを止めたくない」──そんな親御さんの思いに応える教材だからこそ、数多くの家庭で選ばれ続けています。
発達障害の子どもに「すらら」が合う4つの理由
- 得意・不得意の落差に対応し、成功体験を量産する「無学年式」
- AI × アダプティブ学習機能
- ゲーミフィケーション × トークンエコノミー
- 休会・再開の柔軟性
理由01|得意・不得意の落差に対応し、成功体験を量産する「無学年式」
発達障害の子どもは、教科や分野によって得意・不得意の差が大きい場合があります。
例えば、算数の計算は得意でも文章題が苦手、国語の読解が難しいが英語の音読は好き…など個性はさまざまです。そもそも学校の授業は集団で同じペースで進むため、「わからないところ」が置き去りになってしまう子が少なくありません。
すららは「無学年式」の教材なので、学年に縛られずに必要な場所から学習を始められます。苦手分野は小学校低学年レベルに戻って基礎からやり直し、得意分野は学年を超えて先取りし、「できる!」という達成感がどんどん積み上がっていきます。
すららの無学年式教材では、「つまずきを解消する」と「得意を伸ばす」を同時に実現。小さな成功体験を積み重ねることで、自信を育み、学習意欲の向上につながります。
理由02|AI × アダプティブ学習機能
すららのAIは、お子さまの解答パターンや間違い方を細かく解析し、「なぜつまずいたのか」を特定します。例えば、分数の問題ができない場合でも、実は掛け算や約分の理解不足が原因かもしれません。こうした“根っこの原因”をAIが探り出し、必要な単元までさかのぼって学習できるのが特長です。
さらに、つまずきの穴を見つけて埋める作業を自動で繰り返す「アダプティブ学習機能」を搭載。学年の枠にとらわれず、基礎から復習しながら確実にステップアップできます。
理由03|ゲーミフィケーション × トークンエコノミー
発達障害の傾向にあるお子様の特性の1つとして挙げられるのが「収集癖」です。
そこに着目し、採用したのが「ゲーミフィケーション機能」と「トークンエコノミー方式」です。ゲーム感覚で楽しく勉強し、頑張った分だけポイントが貯まり、そのポイントを利用してアイテムを集めることができるのです。

この仕組みが、お子さまの学習継続の大きなモチベーション引き上げをサポートします。
理由04|休会・再開の柔軟性
すららには休会制度があり、利用を一時的に止めても追加費用はかかりません。
再開する際も入会金などの費用は不要です。
さらに、すららは無学年式なので、途中で休んでも続きからスムーズに再開でき、過去の内容を振り返ってやり直すことも可能です。
休会も再開も「費用や学習面でのストレスが無い」ため、子どものやる気が落ちたときや体調が優れないときでも、安心して休会という選択ができるのが嬉しいポイントです。
出席扱い制度と活用事例
出席扱いになるための条件(文科省の7要件)
近年、文部科学省ではICTを活用した学習でも一定の条件を満たせば出席扱いにできる制度を整えています。すららはこの要件を満たす教材の一つです。主な条件は以下の7つです。
- 学校長が認めること
- 保護者と学校が連携を取っていること
- 計画的な学習プログラムに基づくこと
- 学習内容が指導要領に準じていること
- 学習の記録が残ること
- 定期的な評価や確認があること
- 学習結果を学校に報告できること
- 文部科学省は令和元年に「出席扱い制度」を発表
これらをクリアすることで、学校に行けない日も「学習」として認められ、出席扱いになる可能性があります。
学校への申請方法と提出書類
出席扱いを受けるには、まず担任や学校長に相談することから始めます。
すららでは、出席扱いの申請に使えるフォーマットや学習記録の出力機能があり、提出書類として使えます。
例としては、1日の学習計画、進捗報告、テスト結果の提出など、出席扱いの申請をサポートする機能があらかじめ備わっているのは学校とのやりとりをスムーズに行うことができて効率的です。
出席扱いを受けた家庭の実例
発達障害の子どもは体調や気分の波で登校が難しい日もあります。そうした場合でも、すららを利用して自宅で学習し、出席扱いになった事例があります。
ある家庭では「学校に行ける日は通学し、休みの日はすららで計画的に学習」、学習ログを学校に提出することで、無理なく学習と出席を両立できました。こうした柔軟な使い方ができるのもオンライン教材の強みです。
実際の体験談・インタビュー

机に向かうのが苦手だった子が変わった!ゲーム感覚のごほうび学習

小学校4年生の男の子のママ
発達障害のある息子は集中力が続かず、机に向かうだけで泣いてしまう日もありました。そんなとき出会ったのがすらら。問題を解くたびにポイントが貯まり、家での小さなご褒美と交換できる仕組みが、息子のやる気スイッチを押してくれました。「あと1問だけ!」と笑顔でタブレットに向かう姿を見たとき、胸が熱くなりました。
泣き顔から笑顔へ。AIが見つけた“つまずき”克服の道

小学校3年生の女の子のママ
算数の文章題になると手が止まり、イライラして泣き出す息子。親としてもどこを直せばいいのかわからず悩んでいました。すららのAIは間違い方から原因を特定し、「割合の理解が弱い」と示してくれました。自動でさかのぼり学習を進めるうちに「わかった!」と笑顔が戻り、その瞬間、親の肩の力も抜けました。
学校に行けない日も安心。すららで「欠席」を「学びの時間」に変えた話

小学校3年生の女の子のパパ
朝になると体調や気分が揺れて登校できない日々。親として「勉強が遅れるのでは」と不安でいっぱいでした。そんな中、すららは出席扱いの申請フォーマットや学習ログが整っており、学校の先生も理解がありスムーズに認めてもらえました。「今日行けなくても学びは止まらない」と感じた瞬間、心から安心できました。
親も子も救われた。寄り添ってくれる“すららコーチ”の存在

小学校4年生の女の子のパパ
学習が進まない時期、親子ともに疲れ果てていました。そんなとき、すららコーチが「今日はここまでで十分」「褒める言葉はこうしてみましょう」と優しく伴走してくれました。休会を勧めてくれたときも責められている感覚はなく、「無理しなくていい」と寄り添ってくれたことで救われました。子どもの小さな成長を一緒に喜べる存在に、親としてどれだけ励まされたかわかりません。
【すらら体験談】無料体験で実感!発達障害の子が続けやすいと評判の理由

すららと他のオンライン教材との比較
比較表(すらら・スマイルゼミ・スタディサプリ)
| 項目 | すらら | スマイルゼミ | スタディサプリ |
|---|---|---|---|
| 発達障害・不登校への特化度 | 高い 発達障害・不登校支援を公式に掲げ、専門家監修あり | 中程度 特化はしていないが利用実績あり | 低い 一般向け教材、特化なし |
| 専門家監修 | あり(教育心理・発達障害の専門家が参画) | なし | なし |
| 出席扱い制度 | 対応可・実績多数(全国で学校出席扱いに認定されるケース多い) | 原則不可(ほぼ実績なし) | 原則不可(実績少ない) |
| 学年方式 | 無学年式(小1~高3まで柔軟に行き来可能) | 学年式+一部無学年式(国語・算数は中3まで対応) | 学年式(先取り・戻りは可能) |
| 対応教科 | 小中高5教科(国・数・英・理・社) | 小中全教科(国・算・理・社・英・プログラミング等) | 小中高全教科(動画授業形式) |
| 学び方 | アニメーション授業+ドリル+AI最適化(ゲーミフィケーションあり) | タブレット教材で演習+自動丸付け | 講義動画視聴+確認テスト |
| 先生役 | キャラクター先生+すららコーチ(人間サポート) | 先生役はなく教材中心 | 人間講師(有名塾講師) |
| AI技術の活用 | あり(AIが弱点を解析し、最適問題を提示) | あり(AIが苦手分析して出題) | 一部あり(おすすめ授業提示程度) |
| 休会制度 | あり(休会中は料金不要/再開時に入会金不要) | なし(解約→再契約/再契約時に入会金必要) | なし(解約→再契約/入会金不要) |
| 入会金 | あり(約11,000円)※初回のみ | あり(約2,000〜3,000円)※再契約時も必要 | なし |
| 途中解約の違約金 | なし(休会も可) | なし(ただし専用タブレット代残金一括精算のケースあり) | なし |
| 専用タブレット | 不要(PC・タブレットで利用可) | 必要(専用タブレット代約1万円〜) | 不要(PC・スマホ・タブレットで利用可) |
| 料金目安 | 月額8,800円~ | 月額2,980〜3,278円+専用タブレット代 | 月額1,980円〜(個別指導は+9,800円) |
| 無料体験 | 無期限体験あり | 約2週間無料 | 14日間無料 |
| すらら | 特化型・安心サポート・出席扱いの実績・休会制度とすべての面で強く、「学習習慣がつかない」「不登校や発達障害がある」「親もサポートに不安がある」家庭の第一候補 |
|---|---|
| スマイルゼミ | 学習習慣化やコスト面を重視する家庭に合うが、発達障害対応は限定的 |
| スタディサプリ | 低価格で映像授業が強み。学習意欲が高く、自己管理できる子向け |
すらら
発達障害・不登校対応に特化した安心教材
すららは、発達障害や不登校の子どもに寄り添う設計が最大の特徴です。無学年式なので、得意な教科は先取りし、苦手な単元はじっくり戻れる柔軟性があります。アニメーションキャラクターが先生役となり、親しみやすく学べる点も魅力です。さらに、「すららコーチ」という専門スタッフが学習サポートを行い、家庭の負担を軽減します。発達障害や教育心理の専門家が監修しているため、子どもに合ったペースで安心して学べます。加えて、全国の学校で出席扱いとして認められる実績が多く、学習継続が社会的にも評価される点は大きな強みです。休会制度も柔軟で、再開時に入会金が不要なので、長期的に安心して利用できます。
スマイルゼミ
タブレット中心で日常学習の習慣化に向く
スマイルゼミは、専用タブレットで学習するシンプルな教材です。日々の学習メニューがわかりやすく表示されるので、習慣化しやすい設計になっています。国語・算数は無学年式で中学レベルまで対応しており、家庭学習を幅広くサポートします。AIによる苦手分析もあり、成績アップを目指せますが、発達障害・不登校に特化した機能や専門サポートはありません。休会制度がないため、学習を一時中断すると再契約が必要で、再開時に入会金もかかる点がデメリットです。コストや習慣化重視で、比較的定型発達のお子さんや、親が日常的に管理できるご家庭に向きます。
スタディサプリ
コスパ重視の動画授業
スタディサプリは、低価格で有名講師の授業動画が見放題という点が魅力です。映像での解説がわかりやすく、特に意欲的な子どもには有効です。講義内容は質が高く、受験や進学準備にも活用できます。一方で、発達障害や不登校に特化したサポートはなく、出席扱い制度の対象にもなりにくいため、家庭での管理や声かけが重要です。休会制度はありませんが、解約と再契約のハードルは低く、入会金も不要です。補助教材や追加学習として導入する家庭に向いています。
まずは、学習習慣を身につける段階のお子さんの場合
家庭で机に向かう習慣がないお子さんの場合は、もっと短時間でゲーム感覚の教材から始めるのも有効です。
| すらら漢字アドベンチャー | 認知特性に合わせて漢字を覚えるアプリ。短時間で取り組め、机に向かう習慣作りにおすすめ |
|---|---|
| そろタッチ | 暗算や計算力をゲーム感覚で鍛える教材。集中力が続かない子や計算が苦手な子の導入におすすめ |
これらを併用しつつ、最終的には総合的な力を育てる「すらら」へスムーズに移行できる流れを作るのも効果的です。
「すらら」をうまく活用する5つのコツ
01|机に向かうまでのハードルを下げる「5分ルール」
発達障害のお子さんは最初の一歩が大きなハードルです。すららを始めるときは「まずは5分だけやろう」と声をかけ、短時間で終わる安心感を与えるのがおすすめ。やり始めると集中し始めることも多く、小さな成功体験を積むきっかけになります。
02|トークンで達成感を可視化
5分ルールで机に向かったら、次はやる気を持続させる工夫。すららのトークン機能は、問題を解くとポイントが貯まり、成果が目に見える形で残ります。親子でご褒美を設定すると、達成感が増して「もう少しやってみよう」という気持ちにつながります。
03|苦手の原因をAIが特定
短時間学習でも効果を高めるには、何が苦手なのか知ることが大切。すららのAIは間違い方を分析して原因を特定し、自動でさかのぼり学習を提案します。親も子も「どこからやり直せばいいの?」と迷わず、無理なく理解を積み重ねられます。
04|無理に登校させず、出席扱い制度を利用
気分や体調に波があり登校できないことが続くと、大変ですよね。そんなときは無理に学校に登校させず、すららで「出席扱い」の申請をお試しください。すららなら学習ログやフォーマットなど、出席扱いに必要なデータが整っていて、導入実績も多いことから学校とのやり取りもスムーズです。
05|コーチの伴走で継続をサポート
学習のリズムが乱れがちな時期も、すららコーチが相談にのってくれます。「5分だけでもOK」「ここを褒めましょう」といった具体的なアドバイスは、親子の負担を減らし、前向きな気持ちを保つ助けになります。すららは発達障害のお子さんのいるご家庭のサポートも経験豊富です。まずは気軽に相談してみてください。
よくある質問(FAQ)
まとめ
発達障害の子どもを持つ保護者にとって、勉強や学校生活の不安は尽きません。「体調の波で学校を休みがち」「勉強の遅れが心配」「家ではどうやってサポートすればいいの?」と悩むことも多いでしょう。
すららは、そんな悩みに寄り添うオンライン教材です。無学年式で苦手な単元は戻って学び、得意な分野は先取りできる。キャラクター授業や褒めて伸ばす仕組み、コーチの伴走で、子どもも安心して取り組めます。
また、学校と連携すれば出席扱いになる可能性もあり、家庭学習を正式な学びとして評価してもらえるチャンスがあります。休会や再開も柔軟なので、体調ややる気に合わせて続けられるのも強みです。
もし今、「勉強や学校生活でつまずいているかも」と感じているなら、まずは行動してみることが大切です。
無料体験を通じて教材の使いやすさやお子さんとの相性を確認し、学校との相談にも活用してみてはいかがでしょうか。家庭でも安心できる学習環境を整え、子どもの「できる!」を一緒に増やしていきましょう。